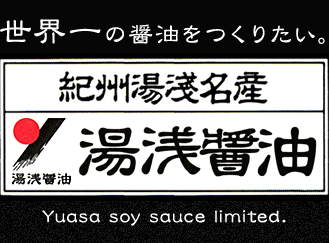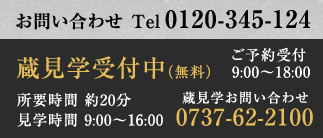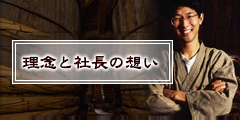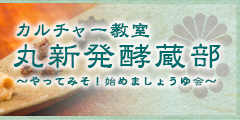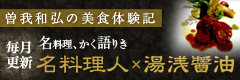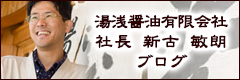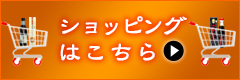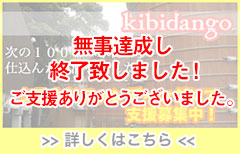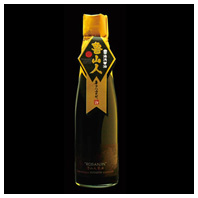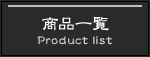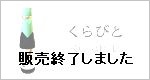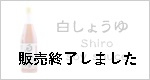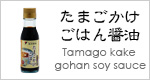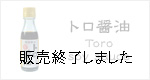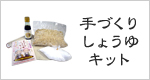136 2025年02月料理人には色んなタイプがいる。同じものをひたすら作り続けていても飽きない人もいれば、色んな事を試して刺激を求めたい人もいる。今回紹介する「西天満 桜会(さくらえ)」の店主・満田健児さんは、勿論後者のタイプ。かなりの理論派で、物事をとことん突き詰めて行く方。だから店に行くと、面白い料理に出合える、話を聞くとその工程のユニークさに驚かされる。「新たな古典を作りたい」と模索する満田さんの店を訪れたくなった。そこで湯浅醤油・丸新本家の商品を予め送っておくと、その特性をいかにいかすのだろうかと取材したくなったのだ。今回は、将来の古典を考案中といわれる和の名人の店で醤油・味噌の調理工夫を追求してもらった。さて満田さんは、いかなる料理を登場させたのであろうか。
西天満 桜会(さくらえ) 満田健児
(西天満 桜会 店主)
 「魯山人醤油は、色は濃いが
「魯山人醤油は、色は濃いが
しょっぱくないのがいい。
切れがいいからか、
舌には残りません。
素材とうまく組み合わせる事で旨みの相乗効果も狙えます。」
新たな古典料理を完成させたい!


取材をしていて楽しいのは、料理をとことん突き詰める人に出会った時である。特に理論派は、納得できるようなワードが得られるために書きやすい。何にしてもそうだが、こだわりのある人や発想がユニークな人は、色んな出合いをもたらせてくれる。我々の仲間内では、物事を突き詰める人や、常にユニークな発想をし、具現化する人を畏敬の念を込めて〝変態″と呼んでいる。湯浅醤油の新古敏朗さんも“変態”の一人で、ボルドーで醤油造りを始めたり、湯浅の海に醤油を沈めて海中で熟成させたりと、まさにユニーク。常人がやらない事に取り組んでいる。その行為こそが“変態”たる所以で、彼は「変態の20則」(プレジデント社刊)なる本まで出版している。とにかく“変態”は、発想が自由で、ものづくりが個性的。こちらとしては、取材対象として面白くて仕方がない。
今回紹介する「西天満 桜会(さくらえ)」の店主・満田健児さんもまさにその部類に属する人であろう。私のブレーンの一人である田中愛子先生とも懇意で、満田さんの話は田中愛子先生を通じて伝わって来る。長年豊中で店(懐石料理とよなか桜会)をやって来てその二号店として西天満に日本料理店を出したのは聞いていたが、満田さんの話では、「西天満 桜会」を出店してからすでに4年が経つらしい。私は、ここ一~二年ぐらいの出店ではないかと誤解していた。情報を常に色んな角度から獲るためには諸ゆる所にアンテナを張り巡らせてないといけないと反省した次第である。ところで私と満田さんの出会いはいつだったろうか?きっかけは、確か当時ゴマ屋(和田萬)の専務だった和田大象さんに食事に連れて行ってもらった事に違いない。その時の料理がよかったのと、話が面白かったのですぐに日経新聞Web版連載コラムの取材を申し込んだのを覚えている。以後は田中愛子先生を通して色んな所で顔を合わす事が多々あった。私は最近ふと思った。満田さんほど取材対象として適任な人はいないのに、なぜかこのコーナーで取り挙げていないのだろうと_。そこで昨年末に思い切って「名料理、かく語りき」の取材をさせてもらえないかと申し込んだのだ。満田さんには予めいくつかの湯浅醤油・丸新本家の商品を送っておき、それらを使って料理を考えて欲しいと伝えてあった。私は満田さん自身のこだわりや料理の考え方を多少は知っていたので、取材日はかなり期待して出掛けたのである。


ここで少し満田さんの事について触れておこう。満田健児さんは、「懐石料理 桝田」(心斎橋)の桝田兆史さんに師事している。桝田兆史さんにとっての初めての弟子に当たるようだ。かといって満田さん自身は「桝田」で働いておらず、桝田兆史さんが独立前に料理長を務めていた「榎里(えさと)」で一緒に板場にいたらしい。あべの辻調を出たてで8年間桝田兆史さんに日本料理を教わったという。その後、満田さんは、老舗「なだ万」に移り、大阪の店で働いた後に独立している。今でこそ満田さんが営む「懐石料理とよなか桜会」は、豊中の通称ロマンチック街道沿いに位置しているが、当初は岡町近くにあったらしい。初めは夜だけの営業で単品ばかりを出していたそうだが、やがて顧客から「コース料理はできないの?」との要望があり、それを実現させたら次は「昼営業をやらないの?」との問い掛けもあってそれを次々と具現化しているうちに今のスタイルになったようだ。やがて満田さんは個室が欲しいと思い出し、縁があって今の豊中の店に移ったという。「現在は豊中と西天満の二店舗を営んでいます。実は豊中の駅前でおでん屋をやっていた時期もあって考えてみたらずっと二店舗をやっている計算になるんですよね。そのおでん屋は今は閉めてしまいましたが、コロナ禍に友人にここ西天満の物件を紹介されて、また二店舗目をやる事になったんです」と満田さんは「西天満 桜会」を開くきっかけを話してくれた。当初は北新地で二号店をとの話もあったそうだが、「せかせかするのがあまり好きではない」との理由から御堂筋を挟んで東側に位置する、かつて老松町界隈と呼ばれた西天満の地で店を構える事になった。「西天満 桜会」は、カウンター7席、テーブル(4人席)が4つという丁度いい具合のスペース。奥のテーブル席は個室としても使える。周辺は裁判所があって法曹関係者も多く、グルメも沢山いるので立地としてはぴったりなのだろう。
満田さんは、自身の店に“誰かに教えたくなる日本料理を”のキャッチフレーズを揚げている。平安期に貴族は花見の宴を開き、美酒美肴に酔ったとされる。その宴を“桜会(さくらえ)”と呼ぶ。日本料理には、先人達が飽くなき追求をして技術を磨いた結果、今の技法や代表的料理が誕生している。満田さんは、そんな伝統の技を大切にし、もう一歩進ませる事で新たな古典を作ろうとしている。そこに達するには、基礎は必要で決して創作に走らず、百年後に古典として伝わるような料理にしたいと考えているようだ。「私は落語が好きで、そんな落語の中でも桂米朝さんの作った話を古典だと思って聴いてる人達が沢山います。私もそうなるように料理を考えて行きたいと思っているんです」と話してくれた。


例えば「鱧ちり」は、どこの料理屋でも出て来るものだが、「桜会」ではいささか調理工程が異なる。大抵は、沸騰した湯に薄く切った鱧を入れて氷水に落とす。水を吸った鱧の身はどことなく水っぽかったり、旨みが抜けてまったりしている。だから、梅肉の濃い味を付けるのだ。ところが「桜会」では、100℃で油通して鱧ちりにしている。「100℃の油に浸けても鱧の身は縮まないんです。油だと100℃なら沸点に達していないので身の持つ旨みが外に出ないんですよ。100℃だと油は対流せず、皮目に火が入りきるくらいに。このようにして俗称“油ちり”した鱧を丘上げすると、自分の熱で油を落としてくれます。だから油で揚げたようなしつこい味にもなりません」。油通しされた鱧は、しっとりして旨みが生きている。客側は、そんな工程はわからないが、食べると「なんでこの鱧は美味しいの?」と聞いて来るという。こういった油通しをする事で「桜会」では、鱧本来の味を伝えようとしているのだ。なのでこの店では、鱧の落としは梅肉を添えておらず、紫蘇酢で味わう。油通しの手法なら濃い梅肉で食す必要はないというわけだ。このようにして満田さんは、古くからある料理を満田流の新しいスタイルに変えて行っている。この新たな手法が百年後に古典になるのを目指して調理しているというのだ。
商品の味をいかして調味を施したい


さて、湯浅醤油・丸新本家の商品を使って満田さんはいかなる工夫をしたかというと、取材日には「柚子梅つゆ」「魯山人」醤油、「あえみそ」を用いて三つの料理が作られていた。正式な料理名はこの時点ではまだ存在しないので、仮りに①鰤の炭火のタタキ②牛ハラミの甘酢あんかけ③帆立のピカタとしておこう。
まず「鰤の炭火のタタキ」だが、鰤は氷見の天然ものを使っている。鰤は高温の炭火で焼いているのだが、四つある面のうち三面を軽く霜降り状態に炙り、皮目だけパリッとなるまで焼いていく。皮目だけは、鰤の内側から出る油で唐揚げのような状態にしてカリッとさせるのだという。満田さんによると「オーブンでは火が入りすぎるため、炭火でないといい具合いに焼けない」そうだ。このようにして焼いた鰤に紅芯大根のおろしを挟み、上からだしで割ってとろみをつけた「柚子梅つゆ」を掛けている。そして天には四川山椒の新芽と穂紫蘇を載せている。「柚子梅つゆ」は、このままでも使えそうな完璧な味だと満田さんは評していた。当初はジュレにしようかと思ったらしいが、それだとつゆの味が強く感じてしまうのでだしで割ってとろみをつけて使っている。「この商品は味がしっかりしていて酸味もあるからその香りを引き立てるべく穂紫蘇を用いました。天に盛った四川山椒の新芽はかなり刺激的で、そこにもう一つ香りを足したいと思い、穂紫蘇を用いたんですよ」。紫蘇と合わせる事で風味が増していく。満田さんは、これまで自分が積み重ねてきた記憶の中でもう一つの香りを必要として探し、その香りでこの料理を昇華させようとした。食べると鰤は酸味が抑えられて丁度いい塩梅(あんばい)になっていた。四川山椒がピリッと来て刺激を与え、紅芯大根が鰤の風味をうまく味と調和させているように感じた。満田さんは、この料理で調味した「柚子梅つゆ」と高く評している。「例えば、鰹のタタキは、塩をしてポン酢をかけるのですが、この商品なら何もせずともそのままかけるだけでいい。ご飯にかけても酢飯のように感じるのではないでしょうか」と話していた。


二品目の「牛ハラミの甘酢あんかけ」は、ハラミを塊のまま天ぷらにし、後から切って盛り付けている。その下には、黒酢と「魯山人」醤油、黒糖、昆布と鰹節の合わせだしで作った甘酢に葛でとろみをつけたものを敷いている。ハラミを使った理由を尋ねると、「魯山人醤油があまりに完成度が高かったので肉と組み合わせてもいいと思った」そう。ハラミは、赤身の雰囲気を持ちつつも脂気もあるので用いたようだ。「ロースだと天ぷらには向かないんです。むしろハラミはこのソースによく合うから」と素材の選択理由を語っていた。甘酢のソースは、肉の味を引き立てており、しっかりしている割りには舌に残りにくい。牛肉はどうしても味が濃いので舌に残りそうなのだが、この甘酢あんがあるおかげで旨みを出しつつもうまく味が引いて行くように思えた。ハラミを天ぷらにしたのは、和の手法を用いたかったとの理由で、カツにするとどこか俗っぽく映りそうなので採用しなかったそう。普通に行くより何か工夫がしたいと思っていた所に天ぷらの絵が頭に浮かんだと説明していた。「焼くと香りが邪魔になるように思ったんですよ。いい醤油といい酢を使っているから勿体なく感じ、天ぷらなら匂いもつかないからいいかなと…。それに天ぷらは素材を包んでしまうから余計にいいんです。和の雰囲気でまとまるでしょ」。満田さんは、この料理を作ってから「もう少し発展させてもいいかな」と思っていたようだ。完成された料理を出しておきながら、まだまだ飽くなき追求を。そんな点が満田さんらしさなのだろう。


最後の一品は、料理名だけを聞くと洋食っぽい。普通ピカタは、小麦粉と溶き卵をつけて焼いたものだが、この一品は帆立に片栗粉を打って「あえみそ」をたっぷり加えて卵黄で少し延ばしてからフライパンで焼いている。焼くと「あえみそ」が焦げて来るのだが、その焦げが旨いと満田さんは指摘する。皿に金時人参で作ったソースを敷いて上に帆立のピカタを置く。揚げたスナップエンドウと生の甘長唐辛子、スプラウトを添えている。金時人参のソースには、蒸して裏漉しした金時人参を液体化した塩とだし、少しの酢で延ばして作っている。丸新本家の「あえみそ」は、6ヵ月寝かせて造っているから味が深い。満田さんによれば、深みは旨みに繋がるそうで、「この味噌は味のバランスがよく、完成されている」との評価であった。「手軽に造った味噌は、どうしても塩味が立ち、手軽な味にしかならない」らしく、その点「あえみそ」は美味しく、このままでも十分使えると話していた。醤油や味噌を「このままでも使える」と言うのは、料理人にとって最上の褒め言葉だろう。彼らは市販の醤油を買って来ても他の醤油や酒などと合わせてオリジナルの味を作って使用する。味噌もしかりだ。そんな調合は必要ないとの判断から「このまま使える」と評すのだ。


満田さんに商品を渡せば、あれこれと考え、うまく特徴の出た一品に仕上がるであろう。それを期待して今回の取材を設定したが、実に面白い料理が出て来ていたように思う。帰りがけに話していると、「桜会」では夏になると鮎を用いて棒寿司を作るらしい。一般より二回りぐらい大きめの鮎を仕入れ、塩を当ててのぼり串を打って軽く焼く。その鮎を一旦串から抜いて油に浸ける。そして次は蓋の付いたステンレスの容器に入れてオーブンで火を入れる。102℃で5時間火を通すようだ。それを少し置いておくと油が出る。また串を打って炭火で焼いて出すのだ。鮎は工程上、油に包んでいるので香りや味は抜けておらず、中骨や頭まで全て食せる状態に。それをバジルの寿司飯の上に載せ、棒寿司にするのだと言う。一般的に鮎はタデ酢で味わう事が多いが、満田さんはそれが鮎には合わないと考えているのであえてバジルを入れている。米酢で作った寿司飯なのでそのまま食すのが旨いそうだ。こんな話を聞くと、夏場に取材を設けたくなる。春夏秋冬_、色んな季節にその時々の素材を用いて作るのが日本料理のいい所で、四季が味わえるのだ。素材にも四季があるように、調味にも四季がある。先人達は、そんな特徴をうまく出し、古典料理を完成させて来た。満田さんは、さらなる進化を目指し、新たな古典を作ろうとしている。やはり彼は、いい意味での“変態”料理人なのだろう。
-
<取材協力>
西天満 桜会(さくらえ)
住所/大阪市北区西天満4-10-5 H.C.S西天満ビル1階
TEL/06-4397-3987
HP/ Instagramはこちら
営業時間/17:30〜23:00(20:00 LO)
休み/月曜日
メニューor料金/
コース料理 15000円(税・サ別)
筆者紹介/曽我和弘
廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。