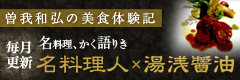123
正月が近づくにつれ、おせち料理の話題が世間を賑わす。コロナ禍では売れに売れ、大手TV通販がそこに参入したからか、その商戦が激化している。早い所は、すでに夏から注文を受け付けており、あの猛暑下で正月の料理はイメージしにくかろうと思ってしまう。こちらの心配はどこ吹く風とばかりにメーカーや料理屋、百貨店には注文が殺到。10月に入ったならほとんどが売れてしまったとも聞く。そんなおせち料理戦線を横目に見ながらそれに因んだ蘊蓄を書くことにしよう。ネタは、おせちに関するもので、そこから飛び火してなますや松花堂弁当にも言及してみたい。正月は、ぜひおせち料理を食べながらこんな話を披露してみるのも一興かもしれない。

- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。
今のおせちのスタイルは、意外と歴史が浅い


やはりこの時季は、年始について書くべきだろう。なので今回は、おせち料理について少し触れたい。旧来、おせち料理は、年末に家庭で作るものだったが、いつの頃からか料理屋で買うものになってしまった。某和食チェーンでは、それが定着し、年末に配達する(もしくは店に取りに来る)おせち料理だけで約一ヶ月分の売上げを計上するという。経営側は、一年を13ヵ月で計算し、その一ヵ月分をおせち料理商戦の売上げを予定しているらしい。その傾向は高まるばかりで、私の記憶が違ってなければバブル期前から「おせちは店で買うもの」になったように思う。年々右肩上がりで推移した傾向に拍車をかけたのがコロナ禍。伝染させては困るとばかりに年始に帰省しない、旅行にも行かない約三年間は、その資金をおせち料理に費やそうとばかりに料理屋や百貨店のおせちが売れに売れ、「おせちは家で作るのではなく、買うもの」との考えがより定着したように思えてならない。今やおせち料理は、本来の概念を飛び越し、洋風から中華風、ジビエおせちに、スイーツおせちまで出て来る始末。重箱に詰め込んでいたなら何でもありなのか。由来や理由をほったらかして「年始に食べれば、それがおせち」との感も否めない。
おせちを漢字で書くと“御節”となる。意味は正月に食す祝いの膳。“節”とは節句を指す。季節の節目に当たる節の日を示す言葉で五節会には儀式を行い、「御節供(おせちく)」を神様にお供えした。ちなみに節句とは、1月7日の人日、3月3日の上巳、5月5日の端午、7月7日の七夕、9月9日の重陽で、陽の数とされる奇数が重なる日がそれにあたっている。但し、1月は、1月1日が元旦なので1月7日を節句にした。中国では、1日を鶏の日、2日を狗(いぬ)の日、3日を猪(豚)の日、4日を羊の日、5日を牛の日、6日を馬の日にしており、7日が人日_、つまり人の日となる。1月7日は7種類の野菜を入れた羹(あつもの)を食べる習慣が中国にあって、それが日本に渡り、七草粥を食べる日になったようだ。セリ、ハコベラ、ナズナ、スズナ、ホトケノザ、スズシロ、ゴギョウが春の七草で、それらを入れた粥を七日粥といい、今でも1月7日に食べる習慣がある。


奈良時代から平安時代には、節の儀式が宮中で行われ、節目の日に邪気を払い、不老長寿を願う節会(せちえ)を設けた。そして御節供(おせちく)と呼ばれる祝い膳が振る舞われたそうだ。ただ、先の五節句もおせち料理も正しく位置づけされたのは江戸時代になってから。化政文化期(文化文政期)になると、お酢のみならず、醤油やみりんも広く調理に活用されるようになり、庶民にも調味料を使った料理が行き渡る。正月料理も定着し、おせち料理に山海の幸が入るように。そして江戸時代後期には、今のようなおせち料理に一つ一つの意味がつけられ、新年を祝う食べ物になって行った。おせち料理を重箱に詰めるようになったのは、江戸時代末期から明治時代にかけてだといわれている。重箱を用いる理由は、めでたさを重ねるの意で、当時はおせちと呼ばずに食積(くいつみ)と言っていた。食積は年始に訪れた人には出すが、これは食べるふりをするだけ。年始客は魚や煮物などをふるまう本膳を食べて帰った。このスタイルが薄れ、いつしか食積がなくなり、重箱に詰めるおせち料理が残ったようだ。おせちといえば正月の料理でその歴史は長いのだろうが、正月料理を重箱に詰めて「おせち料理」として食べるのが当たり前になるのはさらに戦後から。戦前の女学校での教育も関与して徐々に今の形になって行ったよう。起源は奈良時代と古いものの、今のような文化スタイルは昭和_、しかも戦後と意外にも新しい。
醤油が普及する以前は、お酢や煎り酒を活用していた


おせち料理は、概して祝い肴・口取り・焼物・煮物に分けられる。祝い肴にある数の子は子孫繁栄を、黒豆は「まめに暮らす」や「しわが寄る程長生き」に、田作りは豊作の意が込められている。口取りの栗きんとんは金運上昇、昆布巻きはよろこんぶ、紅白かまぼこの紅が魔除けで、白が清浄を表している。あと代表的なものでいうと紅白なます。大根(白)と人参(赤)を短冊に切って酢になじませたものだが、これは水引を指し、縁起ものとされている。
紅白なますに代表されるようになますとは、野菜を酢で和えたものをイメージする。ところがなますの成り立ちはそうではない。なますには、「膾」と「鱠」の二つの字がある。今では、魚貝類や野菜などを細かく刻んで生のまま酢で和えた料理を指すが、古来中国では生肉や生魚を刻んだものの事をそう呼んでいた。秦の時代に入って生肉が使われなくなったために魚肉を用いる事をなますと言った。だから「膾」と「鱠」の二つの字が当てられている。日本では、大昔は中国に放っていたようだが、室町時代にお酢が大量生産されるようになって酢を使うのが定義となって行ったようだ。醤油は、鎌倉時代に湯浅で誕生しているが、全国的に普及するまでに時間を要した。だからその昔は、刺身も酢に漬けて食べていた。そのため刺身の事を鱠(なます)と書く。室町時代以降は、魚介類に限らず、酢で和えたものを膾(なます)と呼ぶようになる。但し、魚のそれと間違わぬよう野菜を使ったものを精進なますという。
ついでに醤油が普及する以前の調味にも触れる事にする。たまに料理屋で刺身(造り)を注文すると、二つの漬けダレが皿に分かれて出て来る事がある。黒い方は当然醤油で、透明な方は煎り酒なのだ。煎り酒とは、室町時代によく使われたもので、いわば醤油代わり。日本酒・梅干・鰹節・塩で作る。しょっぱい梅干を用いる事でだしの味が引き立つ。用途は醤油と同じだが、塩分量は醤油より少ない。江戸時代になると、湯浅の醤油造りが野田や銚子に伝わり、関東で醤油を生産し出したために醤油の価格は江戸の町で下がった。それを機に醤油が一般化。それととも煎り酒はその役目を終えたと伝えられる。今でも時折り昔の食文化を再現するために刺身に煎り酒と醤油の二つを供す店もあるようだ。

おせち料理でお重(箱)の話が出たので、松花堂弁当についても述べておこう。松花堂弁当は、十字の仕切りがあって弁当箱に四つの料理が入っているものをいう。松花堂の起こりは、江戸時代に石清水八幡宮の僧侶・松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)に因したもの。彼は、農家が使っていた種入りの器から絵具箱やたばこ盆を十字に仕切った箱にアレンジして使用した。それが名前の謂れだが、料理とは違う話。この手の箱を料理に用いたのは、料亭「吉兆」の創業者・湯木貞一さんだ。湯木貞一さんは、昭和初期に貴志彌右衞門邸の茶室で茶事が開かれた際に料理を任された。その時出した茶懐石の弁当が箱を十字に仕切ったもの_、いわゆる松花堂と呼ばれる形の箱だった。この料理をその後、毎日新聞が吉兆前菜として紹介した事で松花堂弁当の名が広まった。湯木貞一さんは、箱を十字に仕切り、そこに料理を配する事で味や匂いが移らないようにと工夫した。松花堂弁当の名と形が世間に広まった事で、今ではどこの料理屋でもそれが出ている。配し方で見ためにも美しいためにメニュー化しやすいのだろう。