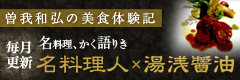52
先月このコーナーで北淡ダコの話を書いたが、やはり旬なので今月もタコにふれておく。但し、今回はタコ焼きがメインで、その誕生秘話を載せることにした。明石や淡路島ではタコ漁がそろそろ最盛期を迎える。6~8月頃のタコを“麦わらダコ”と呼び、この時季が一年で最も旨いといわれているのだ。淡路島には古代のもので出土した土器などを飾る施設があってそこで見た弥生時代のタコ壺は今とさほど変わらぬ形。古代から今のような壺を使ってタコを獲っていたのかと思うと、この分野はそんなに進化して来なかったのか、それとも当時が発展的だったのかと思案することしきり。何はともあれ、夏にタコを語りたい。そう思って今月もタコネタで迫る。

- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。
タコ焼きは、明石から来た客の言葉がヒントに生まれた


海に異変が起きているのか、今年はタコが不漁だと聞く。漁師にいわせれば、地球温暖化の影響は所々で出ており、以前取材した由良(淡路島)の漁師も「真鯖が少なくなった。その代りゴマ鯖が獲れるようになったんです」と話していた。昔はゴマ鯖漁というと、高知だったのが、今は淡路島までそれが上がって来ており、確実に海が暖かくなったことを示している。タコを売りにしている明石浦漁協やら、富島漁協やらも大変で、一番の売れ筋の量が少ないわけだから旬の夏を迎えても高値になりすぎてなかなか流通に乗りにくい。
私は昨年から半夏生の習わしを復活すべく訴求しており、「7月2日頃にタコを喰うべし」と声高に訴えているが、肝心要のタコが高騰するわけだから昔の風習復活とはいきにくい。それでも6月29日に行った神戸酒心館「さかばやし」での食事会「半夏生を前にして明石蛸を夏越しの酒で楽しむ会」は、満席の盛況ぶり。消費者の関心の高さと、旨いもの(明石蛸)への飽くなき追及が窺えた。
タコといえば、やっぱり一番先に頭に浮かぶのはタコ焼きだろう。この料理については、我が知人の熊谷真菜さんが詳しく、彼女が上梓した「たこやき」(講談社文庫)はロングセラーになっている。その本にも書かれているが、タコ焼きは今の「会津屋」が元祖である。福島県の会津坂下町で生まれた遠藤留吉さんが一旗挙げるべく大阪へ来て屋台を始めた。当初はラヂオ焼きという丸い形のものを今里新地で出していた。ラヂオ焼きとは、ラジオのチューナーの形から連想された食べ物で、具材がこんにゃく、すじ肉、豆、ネギだった。その頃、少し流行したのだろう、このメリケン粉で作るおやつは、遠藤さんの母親も作っており、それをヒントに屋台で出していたのだそう。ところが明石から遊びに来たという客が今里新地でそれを買い求めて「浪花は肉かいな。明石ではタコが入ってるで」と言った。彼が言う「タコ入ってるで」は、明石焼きを指す。明石焼きとは、明石以外の人が使う名称で、明石の町では玉子焼きという。この町には明治期から大正期にかけてすでにこの食べ物がすでに存在していたらしい。サンゴ玉の鋳型があり、いつしかその模造(明石玉)に流し込んで作る玉子焼きが生まれたと思われる。そんな玉子焼きを明石から来た客は「明石はタコを入れとるで」と言って遠藤さんに教えたのだろう。

遠藤さんはその言葉をヒントにすじ肉の代わりにタコを入れてみた。すると食感がよく、料理としても旨かった。当時はタコが安かったので、それをラヂオ焼きの具材にして商売を始めた。これがたこ焼きのルーツだ。今もそうだが、「会津屋」のタコ焼きは、醤油味である。それがたこ焼き=ソース味になったのは、当時の流行からだろう。ソースは、ハイカラで西洋料理の代表のような存在。洋食焼きの流行もあってタコ焼きをもいつしかソース味として普及して行った。
考えれば不思議な料理である。「会津屋」の遠藤さんが考案したのは醤油味。何もつけずにパクッと口に入れられるからと、あえて醤油を生地に入れた。それがいつしかソース味のものになって伝播して行くのだ。しかも、遠藤さんがヒントにした玉子焼きは、だしに漬けて食べるものなのだ。こんな話をすると、だしとソースが交わる地点があると某氏はいう。それは兵庫区の御旅町。ここでのタコ焼きは、ソースを塗ったものが、どっぷりとだしに浸っていたらしい。震災で多くを失い、そんな店舗もなくなってしまったろうが、某氏は「御旅町で西からのだしと東からのソースが出合い、融合した」と言って憚らない。
タコ焼きって、本当に大阪の味なのだろうか?


以前、雑誌の取材で出会った玉子焼き店「よこ井」の女将はこんな話をしてくれた。「よくたこ焼きといっしょにする人がいるが、向こうは粉もので、こっちは玉子料理。根本的に違うんです」。大正期に明石の樽屋町では伝説となる玉子焼き職人・向井清太郎さんがその屋台を営んでいた。当時を知る人は、向井さんが作る玉子焼きがことさら旨かったという。その向井さんの配合レシピを手に入れたのが横井金之助さんで、彼の娘が私が出会った横井孝子さんなのだ。「よこ井」の女将・横井孝子さんが私に語った話で印象的だったのは、玉子焼きを漬けるだしは熱いものではないということ。元来、焼きたてはアツアツなのだから、それを冷ます意味で浸すだしがあるのだし、ならば冷たくないと役目を果たせない。考えてみれば納得のいくことで、「玉子焼きの敷き台も斜めである必要がない」との言葉もあわせてさもありなんと思った次第である。
よくテレビなどで大阪の味としてタコ焼きが紹介されることに違和感があった。その最たる理由は、大阪の味なら昆布だしや合わせだしを用いた日本料理が一番に紹介されるべきという私なりの意見なのだが、何だか食の都といっておきながらB級グルメが代表かというのがしゃくにさわったのかもしれない。タコ焼きの歴史を紐解くと、私がそう感じるのもおかしくない。本当の意味と歴史的見地からタコ焼きのルーツとなっているのは明石だし、それを考えた人は会津での食べ物をヒントに屋台を始めている。今では味付けの中心となるソースとて阪神ソースがウスターソースを開発したからで、とんかつソースもオリバーソースが初めて造っている。どこを切り取っても大阪の味ではない。あるとすれば、遠藤さんが今里新地の屋台で誕生させたのと、「会津屋」を設けてから料理研究家の土井勝先生がそれを見い出し、大阪の百貨店の催しで紹介してブレイクさせたくらいである。ウスターソースのことにふれたので少し記しておくと、日本のソースの生みの親は、阪神ソースの創設者・安井敬七郎さん。明治に渡欧し、英国のウスターシャ地方で出合ったソースをもとに造ったのが始まりだ。なのでウスターソースは、日本独特の味になっている。さらにいうと英国でのそのもととなるソースは、ウスターに住む主婦が食材の余り物を調味料とともに保存したままにしていたら、いつしか調味に使えるソースができており、偶然の出来事で誕生したと伝えられる。英国の元祖ウスターソースは、モルトビネガーなどの食酢に、アンチョビやエシャロット、玉ネギ、ニンニクなどが入っており、私達が親しんでいる味とは似て非なるもの。日本の方が甘みが強くて辛みは少ない。

ところで我が家では、元祖に倣ったわけではないが、醤油味のタコ焼きを作る。とんかつソースは、器に出してハケで塗るようにしているが、それを使ってしまうと、どうしてもソースが勝ってしまうので、あまり用いず、だしで溶いた生地に醤油を流し込んで焼いていく。先日、「魯山人」醤油をそれに用いてみたが、やはり醤油の質が上がると味もグンとアップする。何となく上品なタコ焼きが焼けたように思えてならない。タコも明石や富島のものがいいし、醤油とて「魯山人」がいい。富島の漁師から送ってもらったタコを使い、焼いていると、タコ焼きがB級グルメとは言い難いものになっていくから不思議である。