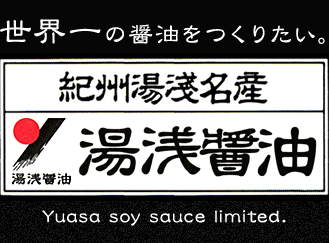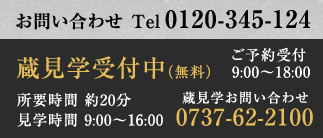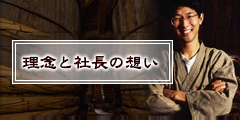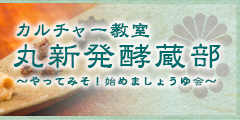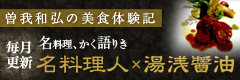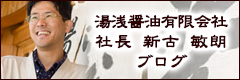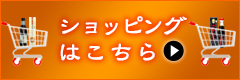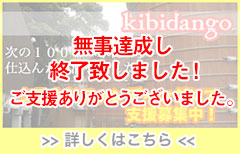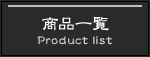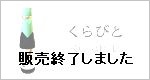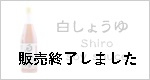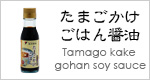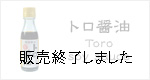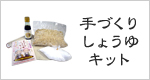136
毎年の事ながら寒の時季は、神戸で催される酒粕プロジェクト発表会の話を載せている。食の多様性と大手日本酒メーカーが高熱液化仕込みを導入した事などが重なって10年以上前に酒粕の流通量が減ってしまった。酒粕を調理利用するのは関西特有の食文化なのに、このままでは酒粕文化が廃れてしまうとばかりに始まったのが酒粕プロジェクトだ。私がそう言い出してから早や11年が経つ。偉いもので毎年プロジェクトを行い、シェフ達に新作酒粕料理を発表してもらうから、いつしかムーブメントになり、ちょっとした酒粕ブームを巻き起こしてしまった。今年も1月23日にマスコミ向け発表会(記者発表会)を行い、2〜3月に参加店舗にて酒粕料理を提供してもらっている。ここでは、その発表会の模様とそれに絡む女子大生の創作についてレポートしよう。
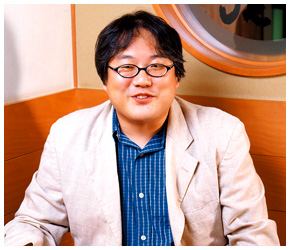
- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。
和の酒粕鍋が伊料理に変化(へんげ)する


寒の時季になると、酒粕プロジェクトがスタートする。2014年に酒粕文化の危機を訴えて始まった同プロジェクトも気がつけば早や11年目に突入する。近年、食の多様化など様々な要因で酒粕の調理利用が促されて来なかった事に因して始まったのだが、毎冬マスコミ発表会を催し、神戸・大阪の飲食店が新作酒粕料理を発表するものだから、今や危機どころか、大きなうねりとなって色んな所で酒粕料理を目にするようになった。そう言えば、和食店やカフェで粕汁をよく見掛ける。先日食事に行った須磨の焼き鳥屋でも寒の時季の無料サービスとして粕汁をふるまっていたし、上本町辺りのカフェでも店の雰囲気とはマッチしそうにない粕汁をランチ時に付けていた。かつては「今更、こんな古くさいものを持ち出さなくても…」と飲食店で敬遠されがちだったのにプチブームが訪れたのか、今では自然と受け入れられている。11年間地道に神戸酒心館の人達と酒粕の調理利用を促して来た結果だと受け止めている。
さて2月1日から3月31日までの2カ月間行われる「酒粕プロジェクト2025」だが、今年も約30近くの飲食店や企業・団体が参加して企画を盛り上げてくれている。コロナ禍以降、マスコミ向け発表会(1月下旬実施)を広めの酒心館ホールで行っており、スペースがあるために多くの飲食店が参加して新作酒粕料理を披露する場になっていた。ところが今年は東明蔵が改装工事に入っているために神戸酒心館の販売コーナーを酒心館ホールへ移さねばならず、酒粕プロジェクトの期間にホールが使えなくなってしまった。そのため同蔵敷地内にある「さかばやし」に発表会の場を移したのだ。ホールだと80名ぐらいの出席者が見込まれたが、日本料理店「さかばやし」の二階フロアではスペースが小さく、その半数以下の収容人数になってしまった。それでもマスコミからの期待は大なのか、TVやラジオ、新聞社などの面々が来てくれ、なかなか盛り上がりを見せた発表会になったと思う。コロナ禍まではずっと「さかばやし」で発表会をやっていたのだから昔に戻ったと思えばそれまでだが、ホールでスペースがあった分、色んな料理人を招いてやっていたので仕方がないとはいえ、発表会に多くの店舗が参加できなかったのは残念に思う。神戸酒心館の話では、「来年はホールが使えるので近年のスタイルの発表会に戻しましょう」との事である。名シェフの新作は来年の発表会に期待しよう。





ところで「酒粕プロジェクト2025」に関しては、いつものメンバーが参加して2〜3月の間色んな酒粕料理を提供してくれている。飲食店だけでも列挙しておくと、サヴォイオマージュ(バー・花隈)、御菓子司 吉乃屋松原(和菓子・松原)、TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST(カフェ・メリケンパーク)、紅宝石(中華料理・元町)、ホテル日航関西空港(ホテル・泉佐野)、日本料理湯木(日本料理・北新地)、キュイジーヌ フランコ ジャポネーズ マツシマ(仏料理・北野町)、北新地ふじもと(西洋料理・北新地)、イルテアトロ(伊料理・和歌山)、日本料理かわもと(日本料理・摂津本山)、嗜酒(小料理&日本酒・心斎橋)、神戸酒心館さかばやし(酒蔵/日本料理・東灘)。これらの飲食店では2〜3月に「福寿」酒粕を用いた料理等を提供しているのだ。
肝心要(かんじんかなめ)の「さかばやし」はというと、今年は大谷直也料理長が新作酒粕料理を出したり、旧来からあるおなじみの「粕汁」や「酒屋鍋」を出したりしてプロジェクトを盛り上げる事になっている。特に「酒屋鍋」は、粕汁の鍋バージョンとでもいうべき一品で、その昔、蔵人達が冷え切った身体を暖めるために食べたといわれる代物だ。魚介類や豚肉、野菜など具沢山の仕様で、酒粕効果も伴って寒の日にはぴったりな鍋料理といえよう。発表会では「さかばやし」の名物ともいえるこの鍋にユニークなアレンジを加える事にした。本来、この手の鍋は締めはうどんと決まっているが、私はパスタを入れて締めを伊料理風に変身できないかと大谷料理長に相談した。事の発端は、うちの学生達を酒粕研究を兼ねて「北新地ふじもと」に連れて行った事にある。藤本直久シェフは、女子大生に酒粕の特性を教えようと、チーズを使わずに酒粕にその役目を担わせてカルボナーラを作っていた。その時の印象が私の頭にあって「酒屋鍋」の締めでパスタを提案したのだ。酒屋鍋の味付けには「福寿」酒粕だけでなく、だしも用いれば、白味噌も使用している。具材の味が出た「酒屋鍋」のだしにさらに酒粕を加え、卵黄と生クリーム、ベーコン、黒胡椒を足し、茹であげたパスタを絡めるようにして作って行く。理由はわからないが、卵黄を入れた時点でなぜか酒粕風味が薄れる。だが、生クリームを加えるや、酒粕風味が不思議と戻って来るのだ。一般的なカルボナーラを作るようにチーズは決して使わない。あくまでチーズの役割を酒粕に担わせて調味するのである。こうして作ると、和食の鍋が伊料理に変身するのだ。出来上がったものは、カルボナーラもどきだが、なかなかいい味に仕上がっていた。神戸酒心館で働くイタリア人のメソレッラ・チンツィアさんにも味見してもらってお墨付きを得た次第だ。発表会では、マスコミ陣にまず「酒屋鍋」を味わってもらい、サプライズとして締めに酒粕カルボナーラを披露した。締めの際には大谷料理長が各テーブルを回らねばならず、なかなか手間取ったが、酒粕の効果を示す意味では面白い発表になったのではなかろうか。「さかばやし」では、普段こんな締め料理を物理的に考えてやるわけにはいかず、店では味わえないが、コラボしてくれた「北新地ふじもと」では要予約で同様の試みを小鍋で行うとの話になっている。もし店で食べたいならそちらへ行って欲しい。ちなみに「さかばやし」では「酒屋鍋」のだしを販売しており、そこには締め用のレシピも添えておくとの話であった。
SDGsを考えて代用食を大学生が提案


「北新地ふじもと」で酒粕の効用について教えてもらった学生達はどうなったのかというと、その勉強の機会が生きたのか、授業でのプレゼン大会で優秀賞を取ってしまった。私は8年くらい前から大阪樟蔭女子大学で教鞭をとっている。週に一回行う授業「フードメディア演習」では、考える事・企画する事を学ぶ場として生徒達に酒粕プロジェクトの参加を促している。新酒ができたらそれに伴って産された新粕を彼女らに手渡し、授業の中でブレストを行いながら酒粕の新たな使い方を模索させるのだ。チームに分かれ、自分が今何を食べたいか?最近印象に残った料理は?など身近な料理から話を進めて、意見を交しながら新たな酒粕料理創作へと導いて行く。生徒達の多くは粕汁さえすすった事がない子が多く、酒粕なんて調理した事がない人ばかり。そんな学生がブレストの中で何とか新たなメニューを生み出して行くのだからなかなか大変。時には酒粕を用いて寿司を作ったり、粕汁を煮物風に表現したり、酒粕饅頭を明石焼風に見立てたり、江戸時代の料理を発掘して来てそこに酒粕をあてがったりと、とにかくユニークな作品が毎年毎年出て来るのだから若い子達の頭はどんな風にも化けると感心してしまう。約2カ月間のブレストを繰り返し、そこで描いた絵を料理として試作する。それから酒蔵の人(神戸酒心館)を学校に招いてプレゼン大会で披露する。コンセプトシートを書き、料理を作って試食してもらうのだ。プレゼン大会を通った優秀作品は、酒粕プロジェクト発表会で披露すると共に2〜3月の2カ月間、神戸酒心館敷地内にある蔵の料亭「さかばやし」でメニュー化されて一般客に提供される。つまり、学生が考えたものが、プロの料理人と肩を並べて売り出されるわけである。







今年その栄誉を勝ち取ったのは、ライフプランニング学科でフードスタディを専攻する三年生の豊川いのり・河内屋柚乃・中西紗和・川本紗貴の四嬢。昨年の11月上旬に「北新地ふじもと」へ連れて行った面々である。彼女達は藤本直久シェフの話をメモを取りながら熱心に聞き、その時に作ってくれた料理をヒントに酒粕がチーズのような代用を果たす事を身を持って知ったようだ。それが創作に生かされていた。このように授業外でも連絡して来る生徒には何らかのヒントを与えてあげる事ができる。要は積極性と創作意欲がこの手の授業には必要で、決して受け身ではいい作品は生まれないとの証明でもある。
豊川さん・河内屋さん・中西さん・川本さんの四人組が考えた酒粕料理は「忘れ去られた麩の焼きを求めて〜釘煮と時雨煮と酒粕あん〜」。巷ではSDGsが叫ばれており、将来を担う大学生には、その手の関心が強いようだ。この作品もそんな発想から創作されている。テーマは「なくなりかけているものの代用食」。メンバーのひとり豊川さんは、「私は釘煮が好きなのですが、近年イカナゴの不漁が目立っており、イカナゴの釘煮を食べる機会が激減しました。何とかそれに似せたものをと考えたのが、今回の麩の焼きに載せた一つの具材です」と話していた。イカナゴが獲れないので釜揚げシラスを釘煮風に作る事で代用食にしようと考えたらしい。その発想が面白いので「三つの具材で一皿を表現してみたら…」とアドバイスしておいた。二酸化炭素を多く排出する牛を飼わない方がいいとの見解も一部にはあるので、将来牛肉が食せなくなったらどうしようと考えて大豆ミートを用いて牛肉代わりにする事を思いついている。大豆ミートを時雨煮風に作って代用食とした。ここで代用食はいいが、肝心の酒粕を用いてないのはどうしたものかと考えた。なので彼女らは、歴史の中から麩の焼きを引っ張り出し、そこで酒粕を使用するようにした。元来、麩の焼きは、小麦粉を水で溶いて薄く焼いて作る。芥子の実などを入れ、山椒味噌や砂糖を塗って生地を完成させる和菓子を指す。千利休が茶会の茶菓子として作らせた事でも知られるものだ。四人は、薄力粉と酒粕を混ぜて水でのばし、フライパンで焼いて麩の焼きを作り、その上に代用食を載せて行った。麩の焼き自身が和菓子要素が強いこともあってお菓子っぽい要素が入ってもいいと考えたのだろう、残りの一つにはあんこと餅を載せ、ここで藤本シェフのアドバイスを参考に酒粕を焼いてチーズ風にして添えている。「麩の焼きは、今はあまり見られないのでその事情も踏まえてネーミングを『忘れ去られた麩の焼きを求めて』としました」と言っていた。ちなみにタイトルは、マルセル・ブーストの小説「失われた時を求めて」をもじっている。よくプレゼンを通るのは時の運ともいわれ、いい作品でも落選する事がある。だが、コンセプトが面白ければ審査員に刺さるのも事実。審査をした神戸酒心館の久保田博信副社長は、「代用食をテーマにするところが、今の若い子らしい。和食に代用食を取り入れたのは、私の知る限りではありません。コンセプトがしっかりしていたので酒粕プロジェクトで発表させてあげたかったし、メニュー化したいとも思いました」と評していた。ちなみにこの四人は、プレゼン大会でもう一作品を発表していた。「モッツァレラと板御神酒で作る200色の酒粕茶碗蒸し」がそれで、こちらは茶碗蒸しを酒粕風にしたもの。モッツァレラチーズと酒粕を入れる事で二つの好相性を示したかったようだ。洋風の味わいがするこの作品は、私が高く評していたが、コンセプトのユニークさから「忘れ去られた麩の焼きを求めて」の方が選ばれている。なにはともあれ、彼女らグループの創作は優秀だった証しである。