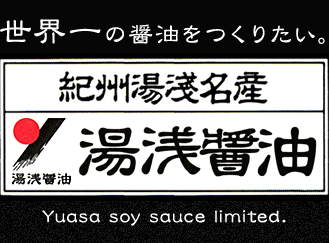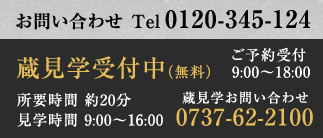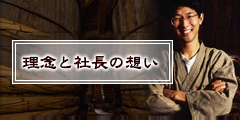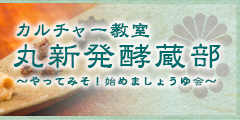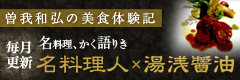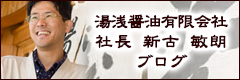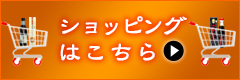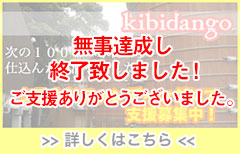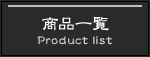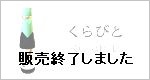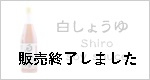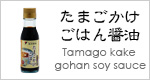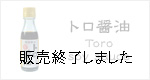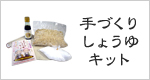138
日本人は手先が器用で、細かい技術によって色んなものが生み出されている。和製料理にもその事例がいくつか挙げられる。料理というのは、事件や祭のように何が発祥なのかはわかりづらい。政治や経済なら文献も揃っているし、その解明も明らかだが、殊、食となるとそうはいかない。色んな所で同時発生なんて例も少なくないのだ。今回は、日本人が作って来た食スタイルについて言及する。今では当たり前となっている事でも、日本独特の習慣からそうなっているというのも沢山ある。思い浮かぶままに日本発祥のものを書く事にしたい。これを読んで少しでも「へぇ~」と感心してくれるだろうか?それともうちが発祥と目くじらを立てて怒るのだろうか?
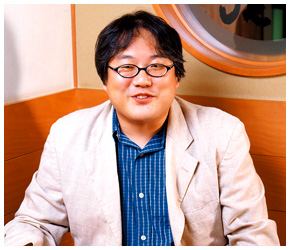
- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。
日本人だからこそ生まれた料理もある

先日、ラジオ大阪の特番「松波キャベツの甘~い話」に出演した。内容は泉佐野産(もん)の松波キャベツの良さについて触れたもの。その中で一緒に出演した藤本直久シェフ(北新地ふじもと)や井口晃一総料理長(ホテル日航関西空港)が松波キャベツを用いた料理についても喋っていた。この放送でパーソナリティーを驚かせたのは、キャベツにまつわる日本と海外の食文化の差。日本人は揚物や焼鳥、焼肉を食す際に生のキャベツを食べるが、実はそんな食べ方(生でキャベツを食べる)をしているのは、日本人ぐらい。欧米人は、まず火を入れて味わう。とんかつの添え物に千切りキャベツがあるが、実はそれを発明したのは日本人なのだ。千切りキャベツの誕生は明治期(日露戦争の頃)。その発祥は銀座の「煉瓦亭」だと伝えられている。同店の木田元次郎は横浜で仏料理を学んだコック。ただ当時の日本人には油やバターをたっぷり使う仏料理が口に合わなかったようだ。仏料理の仔牛のコートレットをアレンジして日本人に合うようにポークカツレツを創作した。仔牛が日本では手に入りにくかったのと、牛肉より豚肉の方があっさりしていいと判断してポークカツレツを作った。ちなみにそれが「とんかつ」と名づけられたのは、上野の「ポンチ軒」らしい。この当時の付け合わせは、ガロニと呼ばれるもの。煮込んだ人参や炒めたジャガイモ、茹でたキャベツがガロニだったわけだ。ところが、日露戦争で若いコックが出兵し、人手不足に。ガロニを作る手が足りなかった。そこで「煉瓦亭」では苦肉の策として生のキャベツを刻んでポークカツレツに添えた。それが千切りキャベツの始まりだといわれている。当時の日本人は、まだまだサラダを知らず、生で野菜を食べる習慣がなかった。最初は「生で食べるだなんて」と抵抗を示した客も食してみると納得。とんかつの油っ気をうまく拭ってくれる事に気づかされたのだ。「キャベツは生の時点で辛みや苦みがあります。その成分が偶然にも揚物にマッチしたのでしょう。口がさっぱりすると評判になってやがてそのスタイルが広まって行ったようです」と「北新地ふじもと」の藤本直久シェフも番組内で語っていた。欧米人は日本人より不器用である。日本人のように細かく切るのは苦手で、欧米人からは千切りキャベツなる手法は生まれないし、今もそれをしないだろうと藤本直久シェフは付け足していた。今では千切りキャベツといえば、とんかつには付き物で、皿の中で当たり前のように存在している。揚物と生のキャベツの組み合わせは、日本人の食文化にうまくはまったのである。


このように我々は当たり前と考えて食しているが、意外にも日本生まれという食べ物(食スタイル)は沢山ある。その一つが焼き餃子。そもそも餃子は、中国で生まれた料理で、宮廷料理(献上品扱い)の一つ。本来は水餃子か、蒸し餃子として食す。その漬けダレも黒酢を用いるのが一般的だ。中国では料理を残すくらい出すのが当然で、沢山作る。餃子も沢山作るわけだが、自ずと残ってしまう。残った餃子は使用人に渡すのが習わしで、もらった使用人は再度茹でても旨くないので焼いて味わったのだ。その手法を鍋貼(コーテル)と呼ぶ。だから中国には焼き餃子なんて言葉はないのだ。それを戦前・戦中に満州で日本人が味わった。焼いた餃子が醤油に合ったのだろう、在留日本人達の味覚に響いた。陸軍関係者を始め、満州にいた支配階級的な日本人は、中国の庶民にその作り方を教えると迫ったようだ。「残飯的な食べ方だから」と初めは断っていた中国人も仕方なしに焼いた餃子を作って日本人に食べさせた。それがきっかけである。餃子の歴史については「元祖ぎょうざ苑」(神戸)の頃末灯留さんが詳しく、彼に取材した話をまた改めて書きたい。餃子というと、にんにくが入っていたり、ラー油を使ったりするのが当たり前になっているが、それとて戦後の日本で生まれたスタイルらしい。戦後、クズ肉やクズ野菜を使っていたので、それを隠す(消す)ためににんにく・ラー油・化学調味料が役立った。そして今では鮮度のいい食材を用いようともそれらを使う事が当たり前のようになっている。頃末さんによると、餃子には中国式、満州式、日式の三つがあって日本で広まっている焼き餃子は日式スタイルと呼ぶらしい。


昨今はインバウンド需要花盛りで、殊、外国人には居酒屋が人気だとか。せっかく京都観光をしても彼らは居酒屋で夜の食事を楽しむらしい。居酒屋とは、酒とそれに合う料理を出す店を指し、レストランや日本料理店とは区別されている。ある人に言わせれば、料理屋と居酒屋の区別は、酒と料理の比率にあるという。前者が料理7対酒3の比率に対して後者は5対5になるらしい。その点でわかると某人は指摘するが、果たして本当なのだろうか。居酒屋の歴史を遡ると、江戸時代にその形がはっきり現れる。酒の量り売りをしていた酒屋で、いつしかその場で飲ませるような所が出てきて、そのうちに酒の肴も出すに至る。居続けて酒を飲むから、文字通り「居酒屋」なのだろう。昨今とは少々形は異なるが、今でも酒屋で肴を出す所もあって今でいう“角打ち”の方が居酒屋の原理に近いかもしれない。コロナの頃は、やり玉にあげられ苦労したようだが、今ではそんな居酒屋スタイルを外国人が好むといって都市では大繁昌しているようだ。食べ物が色々あって酒が安いのがその理由の一つといえよう。そういえば、居酒屋の料理はグローバル。和洋中エスニック、なんでもござれである。先日、三宮のガード下で古くからある居酒屋に入ったが、その店が実に盛況であった。昔はこの手の店はサラリーマン族のたまり場で主は男性客だったが、今は女性同士もいれば、若いカップルもいる。おまけに欧米人も楽しんでいるのだ。私も若い頃は欧州へ行った際に話題先行でパブを覗いたが、そんな感じで外国人も楽しんでいるのであろう。
外国が楽しむ、元祖和製外国料理とは・・・


日本を訪れる外国人に何が食べたいのかと尋ねると、「日本食で好きなのは、寿司とすき焼き」と回答し、続いて「ラーメン、餃子、焼肉」と答えるようだ。そのうちのラーメンや餃子は中華料理だろうがと指摘したくなる。そんな風に思っていると、実はそうでもないらしい。焼き餃子の所でも書いたが、その発祥は中国でも今や歴っとした日本の料理に発展しているという。ラーメンとて同様。中華料理の拉麺は醤油なんて使っておらず、日本のラーメンとは別物。鶏ガラや豚骨でスープを摂り、塩を使って調味する。だから醤油ラーメンは本来、中華料理にないのだ。日本のラーメン発祥には諸説あるものの、大正時代に札幌にあった「竹家食堂」が最初ではないかとの説が有名。これは創業者・大久保昌治の長男の証言をもとに北海道新聞が広めた話らしい。ところが、創業者の四男は「関東の支那そばを持ち込んだもの」と否定している。地域的な事から考えると、中華料理の拉麺は東京や横浜の方が早いと考えるのが一般的かもしれない。醤油ラーメンの発祥は、浅草の「來々軒」で出されたといわれており、明治43年がいわゆる東京ラーメンの文献上の初出となっている。中華の拉麺は開国以降に横浜や神戸で根づき、大正期頃から各地で広まったそうだ。ならば大正期に「竹家食堂」で提供されていた札幌ラーメンの例も納得がいく。戦前まではもっぱらその呼び名は“支那そば”や“南京そば”であったようだ。そもそも拉麺の“拉”の字は、手で引き伸ばすの意がある。手で伸ばして細長い麵の形にするからその字が当てられたのだろう。ラーメンは、中国では拉麺と書いたり、老麺(ラオミェン)と書いたりする。この「ラオミェン」がラーメンの語源かと思いきや、先程の「竹家食堂」が名づけたとの説がまた浮上する。同店の厨房で働く中国人が「好了(ハオラー)」と言っていたのが印象に残り、店主の奥さんが彼のいう「ラー」を取って「ラーメン」と名づけたというのだ。今となってはその発祥なんてわからないが、至る所で「竹家食堂」が出て来るので、この店がラーメン史にもたらした影響が計り知れる。醬油ラーメンの原形は、「來々軒」でチャーシューやメンマを入れたのもこの店といわれている。明治から昭和初期かけては浅草が文化の発信地だっただけにいかにも東京ラーメンの草分けらしい話だ。「來々軒」の創業は明治43年。店主・尾崎貫一が横浜中華街で働いていた広東料理のコック12名を招いて浅草公園前で開業した。ラーメンの他にワンタンや焼売も初めて出したと伝えられているが、真偽はわからない。戦後は八重洲口で店を出していたらしいが、三代目にあたる尾崎一郎に後継者がなくて昭和51年にその歴史を閉じている。店が続いていれば、もっと色んな事がわかったのかもしれない。

最後にもう一つ、洋食についても少し触れておこう。洋食については、以前「名料理、かく語りき」でも書いたが、私は和食の一部だと捉えている。その原形は西洋から来たから仏料理だろうが、日本人が見よう見まねで創作しているから日本人が作った西洋料理=和食と考えるのはいささか飛びすぎであろうか。前段で書いたが、仏料理のコートレットが日本人によってカツレツに変化し、呼び名も“とんかつ”になった。とんかつは、今や和食の一部である。
オムレツは仏料理の“オムレット”から来ている。起源は古代ペルシアにあるといわれているからその存在は古い。オムレットは仏語で剣を意味し、その形状がいかにも剣に似ている事から名づけられた。ならば丸いオムレツは間違いという事だ。そのオムレツから派生した料理がオムライスである。これまた和製洋食で、大阪の「北極星」がその発祥と伝えられている。汐見橋にあった「パンヤの食堂」(北極星の前身)で店主・北橋茂男がいつも米飯とオムレツを注文する胃弱の客に「来る日も来る日も同じものだと可愛そう」とばかりにケチャップライスを薄焼き玉子で包んで提供したのが始まりだと言われている。これがオムライスの発祥と大阪では伝えられるものの、千切りキャベツの発明で紹介した「煉瓦亭」でもまかない料理として誕生したとの話も残っている。溶き卵に米飯とみじん切りの具材を混ぜて焼いたそれは「オムレツライス」と呼ばれ、明治34年よりメニュー化されている。ならば大正14年の「パンヤの食堂」より早い事になるのだ。ただその頃は今のように情報は巷に溢れていない。どこで先に生まれ、それをまねたなんて事もないのだ。なので「煉瓦亭」が創作したものを「北極星」が出したとは思われない。大阪でのオムライスは、大正期の北橋茂男の創作と考えるべきだろう。
ただオムライスにも定義はある。それはチキンライスをオムレツ(薄焼き玉子)で包んだもので、そのスタイルは欧米人には考えられない。なぜなら欧米人は米飯が主食ではないからだ。昨今はカフェなどに“ふわとろオムレツ”や“ふわとろオムライス”という名物料理がある。技術を有すシェフ達がそれを見てどう言っているかというと、「あんなのは腕のない証拠。チキンライスを薄焼き玉子で巻く技術がないからふわとろに納めているにすぎない」と_。彼らにとって“ふわとろオムライス(オムレツ)”は、オシャレでも何でもなく、包めない見本のようなものらしい。「それをオシャレっぽく出しているのはおかしい」とシェフ達は口を揃える。「さもありなん」の御意見である。