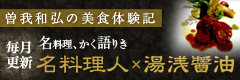71
これまで神戸・元町の「紅宝石」の話は何度か書いて来たし、そこで味わった熊の手料理についてもふれて来た。私は贅沢にもこの珍貴なものを度々食す機会を得ている。そんなことが世間に伝わっているからだろう、「一度熊の手を食べてみたい」と声をかけられる。今回は新年会と称して「紅宝石」で熊の手を中心としたコース料理を提供してもらった。同店は中華料理には珍しく化学調味料を一切使用せず、味も濃くないので身体に優しさを覚える。そんな料理を提供する李さん親子が、またまた私のリクエストに応えて熊の手宴席を催してくれた。湯浅醤油の新古敏朗さんも参加した十日戎の日の宴席について書くことにする。

- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。
この珍貴なものを味わえること自体が
贅沢なのかもしれない!
中国では、昔から珍貴な素材といわれて来た熊の手
十日戎の日に熊の手を食べた。えべっさんと熊は何の関係もなく、昨年から食事会を企画していたらたまたまこの日になっただけである。熊の手料理は、二年に一度くらいの割り合いで食べているだろうか。理由は簡単、私が欲するのではなく、食通がやたら興味を抱き、食べさせてほしいとリクエストするからだ。元来、熊の手は"熊掌"とか"熊蹯"とか書き、中国の珍素材として知られる。龍肝、鳳髄、豹胎、鯉尾、猩唇、鶚炙、酥酪蝉とともに「周の八珍」といわれた。古くから珍貴なものとして食通を唸らせたようで、楚の成王は、反乱を起こした我が子に「熊の手を食べてから死にたい」と懇願したという。中国料理には今でも「紅焼熊掌」というのがある。これは春秋戦国の昔から伝わるもので、柔らかくなるまで煮込み、臭みを取って味を含ませて提供する。春秋戦国というと、周王朝の後半期にあたり、紀元前221年に秦が統一するまでの550年に亘る期間を指す。それが今も残り、現代でも特別料理として宴会にメインディッシュに出るというのだから中国料理の歴史に奥深さを感じる。ところがそんな中国でも熊の手は不足しつつあるらしい。その手の料理ができる人も少なくなっており、昔から珍貴なものだが、今ではそれ以上の価値がついているのかもしれない。
さて、日本の熊料理だが、月の輪熊や羆が生息する、いわば山の料理となり、その土地の猟師が撃ってその地域だけで消費されるとの認識を持つ方がいいだろう。北海道から中部までの一部地域がそれにあたり、熊汁や熊鍋が代表的なもの。日本では年間1000~2000頭が捕獲されており、1割ぐらいが食用として流通するようだ。つまり百頭ぐらいが国内で食べられる熊肉で、当然一頭に手は二つしかないわけだから我々は日本の熊の百分の一を1月10日に食したことになるわけだ。熊というと、一見ゲテモノのように思われるが、肉はなかなか旨い。脂は融点が低いせいで、置いておくと、常温でも溶け出すくらい。赤身もきれいな赤で、クセがない。ただ、野生の動物なので餌に何を食しているかがわからなく、それが因で臭みが生じるともいわれている。猪でも鹿でもそうだが、ハンティングで捕獲されるものは、撃ち所が悪く、苦しんだり、獲ってからの処理がよくなかったりすると、臭みがついてしまう。そのために味噌で匂いを消す料理が普及しているが、腕のいい猟師といい解体処理業者にかかれば、臭みの心配はいらず、しゃぶしゃぶのような食べ方だってできる。但し、それは手ではなく、身の肉を指しての話である。
原材料がすこぶる高く、手間がかかる一品
ところで、私がこれほどまでに度々熊の手料理に接しているかというと、神戸・トアウエスト(元町)にある「紅宝石」を行きつけの店にしているからだ。同店の店主・李松林さんとは長年のつきあいで、そもそものきっかけは彼に「食べろ」と薦められたからに他ならない。噂では、殊のほか熊の手が高価で、両手で9万円を下らないと言われていた。いくら珍貴でも原材料がそれほどするなら料理代金は27万円になると思われる。あまりにも高すぎるからと自身で想像し断っていたら李松林さんは「あなたは物書きだから将来的にみても食べた方がいい」と言っていた。李さんは「その単品だけではなく、コース料理にしてあげるから」と薦め、合計20万円で引き受けてくれたのだ。熊の指は当然ながら10本ある。これを一人一本と計算して10人を集めると、一人の支払いが2万円_、これなら大丈夫だろうと食通を誘った。これが数年前の熊の手初体験のきっかけである。
「熊の手を食べて来た」は、意外にも反響を呼び、「ぜひ機会があれば誘ってほしい」との声が各所より寄せられた。それで一年、ないし二年に一回のわりで「紅宝石」で熊の手を食べる会を催している。会費は、他の料理が異なるためにまちまちだが、それなりに食通達は満足し、李さんから記念にもらったキーホルダー代わりの熊の爪を持ち帰り、土産話にしているようだ。
めったにその会をやるわけではないので、声をかけたが、都合が合わず出席できない人もいる。そんな人からは「次はいつやるの?」との催促が凄く、当方としては度々催す派目になるのだ。その一人が湯浅醤油の新古敏朗さんであった。今回は新古さんのたっての頼みから実現した話で、彼のスケジュールに合わせると、十日戎の日になってしまった。本開催は、李松林さんではなく、息子の李順華さんが調理を担当。彼のレシピの中で熊の手料理や他のコースが展開された。かつて李松林さんが私に熊の手料理を食べるように促したのも息子への技術継承の目的もあった。それほどまでに珍貴なものなので、調理機会を作って伝授したいとの思いがあったに違いない。その格好の相手が私だった。それから思うと、私が度々催しているし、他の客も注文しているだろうから李順華さんにも技術力がついたことを意味している。
よく熊の手はどんな味?と聞かれるが、「紅宝石」で出て来る料理は煮込んだもので、ビーフシチューのような感じと思ってもらえればわかりやすいだろう。コラーゲンたっぷりで、角煮的雰囲気を持つとも加えておこう。李さんによれば、この下処理が大変で、10日~14日くらいの日を要すらしい。それだけ手間がかかるのだから高いのも仕方はない。切断した手には毛がまだある。この毛を抜いて、湯がき、表皮を取り除いたあと三昼夜流水に晒し、液を加えて五昼夜間断なく蒸熱するとものの本に書いてあった。臭みが取れたら骨を抜き、酒や蒜などを加えた煮汁で煮ていくとされているのだ。李順華さんはどのような下処理を施すのかはわからないが、私はこの料理を12月に注文していたのだが、年末に店を訪れた時に李松林さんから冗談まじりに「もうキャンセルするなよ。下処理にかかっているんだから」と釘をさされたくらいだ。
十日戎ならぬ、十日熊の手はやはり十人の食通が参加した。新古さんはもとより「神戸メリケンパークオリエンタルホテル」の鍬先料理長(ステーキハウスオリエンタル)も熊の手を一度は食したいと考えていた一人で、彼のようなプロも加わって来るのが面白い点。単なる食通の集いかといえばそうでもなく、フードコーディネーターや管理栄養士も興味津々で参加している。
この日はオードブルから始まり薬膳スープに、北京ダック、石鯛の冷製料理、熊の手、伊勢エビ、フカヒレの姿煮、葱ラーメン、もも饅頭、デザートと続く豪華版。メインディッシュの熊の手を食べてからも続々と主菜のような料理が出てくるので、肝心の熊の手の記憶は薄らいでしまった。あまりの豪華ぶりに何を喰ったかさえ忘れるほどで、参加者は「メインディッシュをいっぱい食べた」との感想を持ったに違いない。中国の家庭では、これほどかといわんばかりのもてなしをする。むしろ残すくらいでないともてなしにならないと考える。「紅宝石」は、熊の手で誘いながら中国人らしいおもてなしを我々に体験させてくれたのだ。熊の手そのものの味はどうかというと、コラーゲンがたっぷりの肉と答えるしかない。なぜなら独特のクセも臭みも消し、うまく味わうのは「紅宝石」の高い技術あってこそだから。ただ、以前北新地の「肉割烹山口」で食べた熊の肉(身) は絶品で融点の低い脂身は旨い印象を与えた。そう考えると、熊の手も元来、うまく下処理さえすれば旨い素材なのかもしれない。李松林さんによると、若い熊の方がクセが少なく、爪があるかないかで仕入れ値も変わって来るそうだ。爪のある熊の手を北海道から仕入れ、日をかけて下処理し調理してくれた李さん親子に感謝する。