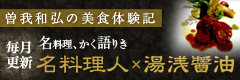50
飲食店花咲りとなり、色んなスタイルの店が街にできた。林立する中で入ってがっかりするのは、その店が本当の個性を有していないこと。どこかのコピーやマニュアル化したものが多く、初めは目立っても内容が伴わなかったり、差別化するものがはっきりとしていないのですぐに終息傾向になる。最近私が注目するのは農業と飲食の距離の近さ。契約農家で作ってもらう云々ではなく、自身で必要なものを育てて使うやり方だ。早々それに合った条件は出て来ないだろうが、やれば確実にコスト削減と料理の良さに繋がる。今回は「遠くのA級ブランドより、近くの新鮮野菜」のフレーズを地で行く二人の経営者のことを書くことにした。

- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。
近いから新鮮をうまく実践している飲食店



「遠くのブランドより近くの新鮮野菜」。こんなフレーズをよく耳にするようになった。宅配便を中心とする流通革命は、我々に遠くの産物を身近にあるかのように見せてくれる効果があった。これにより北海道や信州、九州といった農業大国がブランド化を図り、遠方の食材がどっと街へ押し寄せた。農業大国のものは、土もよく、技術も高いために品質はいいのはわかっているが、殊、鮮度に関しては問題が残る。距離がある分、採ってすぐというわけにはいかないからだ。ところが、都市近郊型農業だからといって採ってすぐに食せるかといえば、その手のものも決してそうではない。JAや市場などを通していると、巷に現れるのはやはり2~3日後。それなら遠方のものと変わらないではないかと思ってしまう。
先日、神戸市北区の苺農家の人と食事をした。北区から飲食店のある東灘区までは車で30分の距離なのになかなかすぐに届けることができないと悩んでいた。宅配便で出せば、翌日到着で鮮度が少し落ちる。かといって毎日そこまで走るわけにはいかず、思うように“近いから新鮮”とは言い難くなってしまうとの話だった。農家でも近いからと配達した人がいたそうだが、渋滞したり、留守で待たされたりして思ったように帰れず、その間に作物をダメにしてしまった例があるようだ。食品バイヤーとして名を馳せる「いただきますねっと」の杉森史明さんも「農家が売ることを重視し始めると、いいものができなくなる」と苦言を呈す。その言葉からすると、近くても自らが配達とはいきにくいのだろう。
“近いから新鮮”をうまく実践している例もある。以前、「名料理、かく語りき」で取材した「農家厨房」(第34回)と「ふく助」(第48回)である。「農家厨房」の大仲一也シェフは、泉州の農家の出身。今でも自身で田畑に入り、栽培している。自家で賄いきれないものは、親戚や友人に頼み、栽培の仕方も指定して作ってもらっている。なので自分でコントロールできるのだ。確かに「農家厨房」で食べた野菜は旨い。自家周辺のものなのでふんだんに使えるのも利点で、ランチメニューには必ず野菜の蒸篭蒸しが付いてくる。これだけでもお得で、まさに自家栽培の成せる技であろう。
大仲シェフは、「遠くのA級ブランドよりも近くのB級ブランドの方が上」と言い、大阪府下の野菜を多用する。“鮮度に勝る旨さはない”との言葉があるように、野菜は鮮度を重視すべきだと彼は訴えている。採ってすぐが実践できるのは、自家の畑なので配達が簡単だから。来る時に持って来てもいいし、誰かに届けさせることも可能。つまりややこしい流通ルートを通していないからである。

三田市で店舗を多く展開している「福助グループ」も同様のことがいえる。居酒屋「ふく助」や「田助」を営む「福助グループ」のオーナー・福西文彦さんも実家が農家。しかも同じ市内の須磨田地区で栽培しているので届けるのに15分くらいしか時間を要さない。福西さんは、20もの店舗を抱える人なので大仲シェフのように今は自らが厨房に入ることはない。なので午前中は畑仕事に勤しみ、昼から店舗を回る。オーナー自身が畑仕事に集中できているのだからさらに利点は大きくなる。農業に関しては新規就農者に畑を貸したり、定年でリタイアした人を雇ったりしながら自分のできない時間や他の田畑をフォローしているのだ。
福西さんの面白さは、彼のユニークな経営術もさることながら大仲シェフ同様に農業を知っているところにある。よく契約農家云々と口にする店があるが、自らが汗を流して作農するのだからこれほど強いことはない。「福助ファーム」(福助グループの農業部門)では、キャベツに白菜、葱、空豆、ブロッコリー、玉ねぎ、小松菜など色んなものを作っている。全て店で使うことを目的としているので、飲食店で必要なものを作っているのだ。「宴会シーズンに入った12月は、白菜やキャベツ、ブロッコリーなどを集中して作ります。鍋物がよく出るとわかっているので白菜は沢山使いますからね。キャベツは余れば餃子を作る工房へ回せばいいですし…」。仕入れる側が自店なので需要と供給のバランスをよくすれば、コスト面にも変わってくるのだ。「福助グループ」は、20店舗もあるから作っても作ってもはくことができる。「5~12月は半分以上自家野菜で賄えます」とは凄い。まさに都市近郊の少量多品種農家の典型であろう。
三田・須磨田地区をアスパラガスの産地に



そんな福西さんが、他への出荷も考えて作付けしているものがある。ハウスで作るアスパラガスがそれ。今は2棟で作っており、全てを自店で使っているが、今年中には7棟へ増やし、来年からは外へも出荷したいと意気込む。聞くところでは、1ヘクタールあれば産地化を名乗れるらしい。福西さん自身で半分ぐらい畑を有す計算になり、あとの半分を周囲の農家に勧めて行えば、いずれは須磨田地区がアスパラガスの産地になるだろうという目論見なのである。福西さんがアスパラガスに目をつけたのは、蒲郡(愛知)でその栽培を目にしたことによる。同地では10アールで、500万円を上げていたそうだ。その範囲は一人で管理できるので面白いと思ったのだろう。現在、農業は何処も高齢化が目立っており、それが深刻な問題としてのしかかっている。高齢になると、白菜やキャベツのような重量物はしんどくなる(標準語では、つらいや骨を折るの意味)。その点、アスパラガスだと重くもないので収穫が楽で、加えて、値段も稼げるようだ。「須磨田は私が若手№3に入るほど高齢化しています。設備投資は必要ですが、これなら収穫が見込めるのではないかと産地化を進めているんです」と福西さん。「福助ファーム」では、アスパラガスのハウスを増やし、手もリタイアして農業をやりたい人を雇えば外へ出荷するまでになると考えている。
福西さんと専業農家(旧来から農業一筋に生きて来た人)には根本的な隔たりがある。それは彼が事業を行って来たので、生産するには人と金をかけないと広がらないとわかっていることだ。「飲食店では、お金をかけて店舗を造ったり、いいものを仕入れなければ差別化は無理。料理もサービスも人を入れねばいいのができません。そんな経験から人とお金が必要で、それをかけないと生産性が上がらないとわかっているんです。農家の人には、そんな発想がない。JAに送って売ってもらうので店や家庭が何を必要としているかもわからないのかもしれません。現在、うちは全ての作物を店舗で使えますし、おまけに末端価格で勝負しているから気ままなこともできる。なので農業も飲食店もうまく行っているのだと思います」。


福西さんの畑でアスパラガスを採ってすぐに南ヶ丘(三田)にある「ふく助」へ持って行き、中野健料理長に調理してもらった。流石に採れたては甘みもあって歯応えもいい。これが流通に乗れば街に出るのは三日後になるという。三日も違えば味は変わるだろう。野菜は採ってからその身を保たせるのに自分の糖を使う。だから日にちがたつと甘みが薄れるのだ。大仲シェフがかつて私に話した「遠くのA級ブランドより、ブランドがなくても近くの新鮮なものの方が上」という言葉が改めて頭を掠めた。「農家厨房」や「福助グループ」のようなスタイルは、よほどの条件が揃わぬ限りなかなかできないだろうが、今後、この手の形の飲食店が注目されることは確実だ。