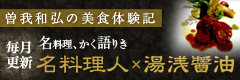132
牛肉はスタミナ源である。暑い時は焼肉を食べてパワーをつけたいものだ。今年はとんでもない猛暑で、秋に入ったというのに連日夏日が続いている。…というわけで秋に入ったにも関わらず、牛肉の話をして少しでも精をつけたい(?!)と思う。牛肉にまつわる話は色々とあるから全ては書けないが、さわりを少し話しておく事にしよう。神戸に暮らしていると、他地方よりは神戸牛が身近に感じるが、だからといって普段食せる代物ではない。世界レベルのブランド品なので我々庶民には高嶺の花である。今回は、肉食禁忌から始まって神戸牛の話まで展開したい。牛肉は単に旨いだけではなく、色んなエピソードがあるのだ。

- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。
すき焼きと牛鍋を混同するなかれ


個人的嗜好の話から入るが、私は猪肉が好きである。脂身がしつこくなく、いくら煮込んでも硬くならない。獣肉系は匂いが苦手と避ける人もいるが、鉄砲で撃って苦しまなければ、肉にまで臭い匂いは回らない。ましてや罠を仕掛けて捕獲すれば、その心配さえない。これは鹿肉にもいえる事で、要は撃たれて苦しむか否かで肉の匂いが違って来るのだ。時にジビエを嫌がる人がいる。ジビエとは、狩猟で得た野生鳥獣の食肉を指す仏語で、猪や鹿、野兎、キジ、鴨の肉をいう。ジビエを毛嫌いする人に聞くと、「牛肉・豚肉・鶏肉なら食すが、それ以外はダメ」と言って頑として受付けない。それでも野禽類のうち、鴨肉はまだ大丈夫な方らしく、「猪や鹿、熊の肉なんてもってのほか!」とばかりに顔をゆがめて嫌うのだ。
こんな状況は、幕末にも似たようなものがあったに違いない。江戸時代には建前として獣肉食が禁じられていた。それを禁ずるようになったのは仏教が原因で、古代は食べていたものの、時代が進むにつれ、一般に仏教が浸透して食べなくなっている。さりとて奈良時代のような昔は、庶民にまで仏教が浸透しておらず、肉食禁止令は出たものの、獣の肉は食べていたようである。特に鎌倉時代の武士は、狩りを盛んに行っており、そこで得た猪・熊・狸・兎などを当然の如く食していたようだ。江戸時代においても上流階級は、獣肉禁忌を守っており、狸汁とてすでに具材は狸肉ではなく、ゴボウ、大根、コンニャクを煮て代用したとある。それでも江戸市中には、獣肉を扱う店もあったそう。近郊の農民が鉄砲などで猪や鹿を撃ち、利根川の水運を利用して江戸市中へ運び入れる。猪・鹿はもとより狐、牛、馬などの肉を食べさせたり、売っていたりしたのが「ももんじ屋」である。一応、肉食禁忌なので、これらの肉を〝薬喰い″と称して食べた。猪肉を「山鯨」といい、猪肉を「牡丹」と呼ぶ。鹿肉を「紅葉(もみじ)」と隠語で言ったりするのは、その名残ともいえよう。大名によっては、それを嫌うものも多く、大名行列は、麹町平河町にあった「ももんじ屋」の前を避けたとの逸話も残っている。



ところが幕末に西洋文化がどっと押し寄せると、獣肉禁忌の流れが一変し始める。牛肉を用いた牛鍋屋に注目が集まったのだ。通説では、文久年間(1861~1864年)に横浜の「伊勢熊」が牛鍋を出し、それが牛鍋の走りとされている。当時、横浜の居留地には多くの外国人が暮らしていた。彼らは、牛肉を取り寄せて食べていたようで、それを知った「伊勢熊」の店主が周りの反対を押し切って牛鍋屋を開いた。特に妻君がかなり嫌って反対したようなので、初めは店の半分を仕切って牛鍋を出したらしい。ところがその牛鍋が大繁昌し、結局は牛鍋屋一本で商売をしたという。
明治2年(1869)には、海軍が栄養をつけるために牛肉を食す事を採用。明治5年には、明治天皇が牛肉を食べた。その事が伝播するや、肉食を奨励するきっかけになり、牛鍋屋が流行するのである。明治4年の仮名垣魯文著「安愚楽鍋」(あぐらなべ)によれば、牛肉を食べる事は文明開花らしく、「牛鍋を食わねば開花不進奴(ひらけぬやつ)」と言って庶民が得意気に食べた様子が描かれている。
牛鍋は、今のすき焼きのルーツとよく紹介されているが、本来それとは微妙に違う。牛鍋は、味噌や醤油で作ったタレで牛肉を煮込んで作る。一方、すき焼きは、浅い鉄鍋で焼いて作る。調味料は、醤油・砂糖・酒・みりんで味噌は用いない。簡単にいえば、牛肉をジュージュー焼くのがすき焼きで、グツグツ煮込むのが牛鍋というわけだ。すき焼きを漢字にすると〝鋤焼″となる。農器具である鋤の背を活用して鷹狩りの獲物を焼いて食べた事に端を発しているのだろうが、別段すき焼きはそうして生まれたわけではなさそう。多分、そんな光景を想像して作った言葉ではなかろうか(諸説あり)。ただ、私はすき焼きとは、その言葉からも焼く料理であって、今のような割下を使い、グツグツ煮るものではないと言いたいのである。この件に関しては、第128回の「名料理、かく語りき」に類似取材があるのでそちらを読んでほしい。すき焼きと牛鍋が合体してしまった要因は、関東大震災後にある。東京・横浜では震災で多くの牛鍋屋が潰れてしまった。その隙に関西からすき焼き屋が首都圏に入って来て市民権を得る。すき焼きといえど、関東では牛鍋のように割下を使う作り方が徐々に浸透し、今がある。それでも平成期の途中までは、関東と関西の作り方は明確に違っていた。割下を用い、牛肉と野菜をグツグツ煮るのが関東式で、関西は牛肉を醤油と砂糖で焼き、それから野菜を入れる。最終的には野菜から水分が出て鍋料理になるのである。それがいつしか店舗でも割下を使う方が楽だと感じ出し、関東式が主流になって行く。調味料メーカーもすき焼き用の割下を開発するので、家庭でも煮る形が当たり前になっている。まさにすき焼きと牛鍋が融合したのだ。

ところで、私は今夏、焼肉をぽん酢で食べるというムーブメントを作ろうとした。関西の焼肉屋を巻き込んで、それを記者発表したのだ。某調味料メーカーの調査によると、関西では焼肉を必ずぽん酢で食べる人は約2割、たまに使うが約5割あるらしい。つまり関西の家庭では、焼肉シーンに何らかの形でぽん酢を行いる人が約7割もいる事がわかった。これは、ラジオ大阪で私が企画した特番前にリサーチしても同じくらいの割合でぽん酢を使うとの結果が得られている。ただこの風潮は関西ならではの現象なので、それを関西からのムーブメントにしようというのが私の目論見である。
一方、焼肉屋では、漬けダレにあまりぽん酢がお目にかかれない。それは焼肉店では、予めもみダレを施すので、ぽん酢を漬けてもそれがはじかれてしまい、あまり効果が発揮できないからである。ならば、種類によってはもみダレをしないものを出してもらおうと、「明月館」や「萬野屋」、あじびるグループの「298PREMIUM難波店」などに協力をあおぎ〝焼肉をぽん酢で″なるキャンペーンを具現化してもらったのだ。
やはり神戸牛は、高嶺の花か!


今夏記者発表した〝焼肉をぽん酢で″の企画には、神戸メリケンパークオリエンタルホテルの鉄板焼ステーキハウス「オリエンタル」も参加してくれている。同ホテルの鍬先章太料理長は、柑橘果汁と米酢でぽん酢(醤油が入っていないもの)を作ってステーキなどに使ってくれたのだ。
我々は、牛肉を食すというと、焼肉とステーキをイメージするのではなかろうか。日本では、ステーキというと、肉を厚くカットした料理を指す。ステーキの語源は、steak(ステーク)に由来しており(諸説あり)、本来は切り身や厚切り肉という意味で使われていた。単純な料理なのでその歴史は古いようだが、日本では欧州のそれより、米国スタイルがむしろ浸透しているようだ。日本で普及したのは戦後で、ビーフステーキを〝ビフテキ″と呼んで食していた時期もある。ステーキは、シンプルな料理なので肉そのものの味が大きく左右する。殊、素材においては世界的に有名なのは神戸ビーフで、先の鍬先料理長の店舗ではそれを多用している。
神戸に暮らしていると、「よく神戸牛を食べるのか?」と聞かれるが、神戸ビーフは高嶺の花なのでおいそれとは食せない。食べるのにン万円もするのだから度々食せる代物ではないのだ。神戸ビーフは、世界にその名を轟かせる名品なのだが、神戸で飼育されている牛ではない。兵庫県で生産された但馬牛から獲れる枝肉が一定の基準を満たした場合に用いるブランド名だ。



明治期の開港直後から横浜同様に神戸にも多く、外国人が居留しだした。彼らは、当時の日本人と違って牛肉を食すわけだから和牛にその素材を求めた。ある時、宣教師が帰国する事が決まり、神戸で送別会を開いたそうだ。その時の食材として但馬牛が使われた。但馬牛には外国の牛と違って細かい刺しが入って柔らかい。送別会に出席した外国人達は、その味がいたく気に入り、「神戸で食べた牛肉が物凄く旨い」とふれ回ったという。横浜でもその噂が広まり、神戸から但馬牛を取り寄せて味わったとの話が誠しやかに伝えられている。
神戸に「大井肉店」なる老舗の肉屋がある。創業は明治4年で、ここでは当然神戸ビーフを扱っている。慶応元年(1865)ごろ、神戸で農家を営んでいた岸田伊之助の所に外国人が来たそうだ。開港準備のために兵庫沖に停泊していた外国商船の船員が「牛肉を食すために牛を売ってくれ」と言って来たのである。当時は日本に肉牛なんて扱いはないので農耕用の牛を求めたわけだ。岸田伊之助は、大事に飼っていた農耕牛をやむなく船員に売ったという。当初は、依頼に応じて近隣から牛を集めて納入するだけだったが、開港する屠牛場もできてさばいた牛肉を納品するように。この話が「大井肉店」の起こりだと伝えられている。では、なぜ岸田伊之助なのに〝大井″と名乗ったのか?岸田伊之助の妻君の旧姓が大井だったから。岸田肉店より、なぜか大井肉店の方がしっくり来たので、店名を大井にしたらしい。
ところで兵庫県で生産された但馬牛のうち、生産環境や肉質で一定の基準を満たしたものを〝神戸牛″というと書いたが、この中には「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」という四つの呼称がある。これは全て同じものを指している。神戸ビーフの基準は色々と細かい規定があるのでここではあえて触れない。ただ、かなりの高級品である事は理解してもらいたい。時折り庶民派の店で「神戸牛の牛丼」やら、「神戸牛の串カツ」が見られるが、あれは本当に使っているのだろうか。リーズナブルには提供できない素材のはずなのだが…。本物の神戸牛には、指定認承マークが交付されている。12枚の花弁の花の中央に〝神戸肉″という文字が描かれ、枝肉の四つの部位に押されている。これが神戸ビーフの証でもある。