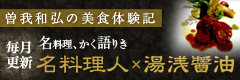26 2015年03月MBS「ちちんぷいぷい」で毎週水曜日に料理コーナーを担当する浦上浩さん。北新地で名を馳せる「石和川」のオーナー料理人である。浦上さんとのつきあいは、かれこれ25年ほど。私がグルメ雑誌に籍を置き、彼に連載「魚は皮がうまい」を持ってもらっていた頃からである。日本料理といえば、鉄鍋で油をなじますのが本流と考えられていた時代に、ひっつかないから楽とテフロンのフライパンを使い、バターなどを用いながら焼魚にソースなどをかけたハイブリッドな日本料理を作っていた。そんな浦上さんだからこそ、誰もが思いつかない手法をやるのではと、「魯山人」醤油、「金山寺味噌」「しょうゆもろみ」の三商品を渡してみた。さて浦上さんはいかに調理したのだろうか。彼が私だけに作ってくれた三品を紹介しよう。
(閉店)粋餐 石和川(大阪・北新地) 料理人/浦上浩
(石和川店主)
 「角がないのでこの『しょうゆもろ
「角がないのでこの『しょうゆもろ
み』は、使いやすいですね。優しい
味がするから関西人には評価が
高いでしょう。今回はだしを使わず、
水だけで豚汁を作りましたが、
その芸当ができるのもこのおかず
味噌の味があったれば
こそです」
昔はハイブリッド、今はエコ



「面白い料理人がいる」。これが「あまから手帖」を創刊した重森守編集長(故人)の浦上浩評であった。この言葉に誘われるままに私は重森編集長と北新地にある「石和川」に来る日も来る日も食べに行った。食に関して厳しい目を持っていた重森編集長は、なかなか人を褒めない。それが連日私を誘ったり、同誌に連載を持たせたりするぐらいだからよほど浦上さんを買っていた(評価していた)のだろう。
浦上浩さんは、MBS「ちちんぷいぷい」にも毎週出演している、関西ではおなじみの顔。だが、この頃は30歳を少し超えたくらいで、まだまだ売り出し中といったところだった。今でこそハイブリッド(和洋折衷)な料理をする所はあるが、’90年代初めはまだ珍しい存在だった。誰もが日本料理とは王道を行くべきで、他の要素を加えるなんてもってのほかと考えていた時代に、さらりとそのスタイルを打ち出したのだから、重森編集長をして「面白い」と言わしめたのもわかる。
浦上さんは魚の町として知られる明石(兵庫県)の出身である。辻学園TEC日調を卒業し、神田川俊郎さんに師事した。北新地の「神田川」では純然たる日本料理は勿論のこと、後年はフレンチに和食の技法を取り入れた「和ふらんす神田川」にも在籍していた。「石和川」でのボーダレス的な調理法は、すでにその時代に培われていたと思われる。浦上さんが23~4歳になった頃、ある人からボストンの日本総領事館で料理をする人を探していると声がかかった。この仕事は総領事の家族の食事を賄うだけでなく、アメリカ(ボストン)の領事館内で催されるパーティーの料理も提供せねばならない。つまり米国の要人を浦上さんの料理でもてなすわけだ。基本的には日本料理だが、ゲストによっては外国のエッセンスも取り入れねばならず、そういった経験が「石和川」オープン後のハイブリッドな料理の背景になっていったようだ。
浦上さんは、都合2年間ボストンで働いた。総領事の異動に伴い、任期を終えて帰国。日本に帰ってからは、「神田川」時代の先輩である坂本さんの店(「味菜」)に居候のような形で入って手伝っていた。この時、以前ボストン行きを世話してくれた人の援助によって独立話が舞い込む。25歳で独立は早いかと一瞬思ったが、先輩の坂本さんも背中を押してくれたこともあり、「石和川」をオープンさせることを決意した。当初は北新地の小さなスペースで開店したが、瞬く間に繁盛し、3年でステップアップしてカウンターと座席がある広めの店へ移転。そこで10年過ごし、今の場所へ移って来た。すでに第1三好ビルで15年が過ぎたそうだ。光陰矢の如しというが、実に早く感じる。私が浦上さんに会ったのは、二軒目の店の時代で、料理人として脂が乗りかかっていた頃であった。「石和川」で展開される会席料理がいかに面白かったか。私は遅くまで仕事をして重森編集長から「めしでも行こうか」と声がかかるのを待っていた。二人で編集部に残り、仕事帰りに行くのは、いつも「石和川」。そして食事は重森編集長のおごりである。時には見解の相違を噂された二人だが、「石和川」では仲良く語らいながら杯を交していた。それができたのも二人ともが浦上さんの腕を認めていたからだろう。


ところで近年、「石和川」を訪れる度に、浦上さんの料理からハイブリッド的なものが消えかかっていることに気づく。洋や中の技法を用いていた料理も、いつしかオーソドックスな日本料理に変化している。どちらかというと、歳を重ねていくうちに王道なものへ思考が変化しているように見受けられる。浦上さんにその点を指摘してみたら、「かつてはハイブリッドでしたが、今はエコかな」とあっさりと認められてしまった。時代の流れを汲んでエコへと行っているように聞こえるが、さにあらず。素材がいい故に捨てるのが勿体なく、余すことなく使い切りたいというのが本音のようだ。「今から思えば…」と前置きしながら明石の魚を使うようになってから徐々に変化してきたのだという。料理屋で明石の魚介類を使っている所は多い。けれどそれらは大半、巷の流通を経たものだ。「石和川」との違いは、その仕入れルートにある。漁場から直送する場合、大概は仲卸しからの仕入れとなるが、「石和川」に限っては漁協からの直接仕入れなのだ。全国でも名高い明石浦漁協から直で取引している所はほとんどなく、知る限りでは私が介してルートを作った「御所坊」くらいではなかろうか。それほど珍しい例で、浦上さんは明石出身だから伝手があってできたのだと思われる。浦上さんは生きた魚のみを仕入れて、いったん自宅内の水槽へ運び、生け越す。そして使う分だけ店へ運んで調理するのだ。なので他店とは鮮度が違う。ましてや東京の料亭が仕入れたがる明石の魚なのだ。質については折り紙つきといえよう。浦上さんの話から考えると、どうやらこうしたルートが確立してから次第に料理が変化していったらしい。「昔は中央卸売市場で仕入れたもので調理していたんですが、それだと誰でも同じ魚を買うことができるんですよ。なので技を駆使しながら一品一品作らなければならなかった。でも今では仕入れた時からすでに他店と差が生じている。なので小細工する必要がなく、自信のあるものが出せると考えたのかもしれません」と浦上さんは自身の調理法の変化を説明してくれた。素材が料理を変えるという話はよく耳にするが、「石和川」の場合は店の売りだった表現方法までチェンジしてしまったのだから、その素材の良さたるや、推して知るべしである。
おかず味噌で、あえて汁物を作った

ところでこの日、私のためにと考案してくれた浦上さんの料理は三品。酒肴盛り合わせと、鱈の白子焼き、「しょうゆもろみ」で作った豚汁である。浦上さんは、「金山寺味噌」「魯山人」醤油、「しょうゆもろみ」の三商品の特性をいかしながら作っている。まず一品目の酒肴盛り合わせだが、皿には八寸風に8つの酒肴とディップが載っている。面白いのは造り風にした生のものに醤油を使わず、金山寺味噌で食べさせようとしているところだ。①伝助穴子の焼き霜に金山寺味噌と梅肉を載せたもの②マグロに金山寺味噌、にんにくスライスを載せたもの③イカの糸造りを巻き、その上に金山寺味噌、刻んだ蕗の薹の載せたもの④湯がいた筍に金山寺味噌、有馬山椒を載せたものの4つは金山寺味噌の味で食べる。一方、ミニトマト、焼いたタイラギ、ホタルイカ、菜の花を目板鰈で巻いたものは、中央のディップをつけて味わうという趣向になっている。ディップにも金山寺味噌は使われており、浦上さんの話では当初はアボカドで作ろうと思ったが、「魯山人醤油・読本」を読むと同じようなレシピが載ってたのでやめて今回のディップにしたらしい。ちなみにこのディップは、金山寺味噌2、絹こし豆腐1、クリームチーズ1の割合いで作っている。「豆腐だけだと、優しすぎるので、クリームチーズを加えました。発酵食品同士だから相性もいいんですよ。今回は用いませんでしたが、マヨネーズと金山寺味噌もよく合います。これもまた優しい味わいになりますよ」と教えてくれた。造りといえば醤油と相場は決まっているが、金山寺味噌の味で食すのもいい。時にはこうして出すのもオツだと、改めて造りの考え方を教えられたような気がする。ディップの方は浦上さんが指摘するように優しい味の中にもクリームチーズのコクが加わり、印象的なものになっている。筍やタイラギなどにつけて食べたが、その後、残ったディップが、これまた酒のアテになるみたいで、箸に塗っては口に運びしながらその味を楽しんだ。

二品目の鱈の白子焼は「石和川」では何度かお目にかかったもの。鱈の白子の筋を取って叩き、醤油焼きにして作る。焼いていくうちに表面に膜ができるのでうまくまとめ、あがりに「魯山人」醤油をかけてバターを落とす。これは浦上さんが鱈の白子をふぐのそれのようにできないかと考案した手法。白子を潰して焼きながら何となく明石焼きのような雰囲気を作ってしまう。食べた方は一瞬、明石焼きかと戸惑いながらも白子の味を実感する。まさに浦上マジックである。「魯山人醤油は飲める醤油ですね。実に味が柔らかく、切れもいい。値段を考えると、飲食店では勿体なくてドボドボと使いづらい。刺身には醤油を入れた器を添えますが、別にそうしなくてもいいはずなんです。塩で食べる時のように数滴落として使うのがいいですね。煮物にしたってこれで煮てもいいですが、それオンリーでは勿体ないように思ってしまう。そんな時はあがりに使えばいいんです。香づけするだけで従来の煮物と差別化できるんですから」。

三品目の豚汁は、「しょうゆもろみ」だけで調味した点が面白かった。一般の味噌ならともかく、おかず味噌で汁物を作ってしまうのが浦上さんらしい発想かもしれない。「鰹だしで作れば美味しく上品な味になるんですが、あえて水だけで作ってみたんです。水に具材を入れ、しょうゆもろみで調味するところがミソですね。安納芋やにんにくはすりおろして入れてます。炊いていくと、豚と野菜からだしが出て鰹だしを使わなくとも勝負できるんですよ。最後のあがりにちょっぴり『魯山人』を使いました」。私が「どうして鰹だしを使わなかったのか?」と質問すると、浦上さんは「だしで作ると、さらに旨くはなりますよ。でも『しょうゆもろみ』を用いると、水だけでもこれだけの味になるんだと証明したかったんですよ」と言っていた。つまり私がこの「しょうゆもろみ」を渡した挑戦状に、あえて遊び心を加えて答えを出してくれたわけだ。だしを用いてないからか、この豚汁は素朴な味がする。汁の中にもろみの粒が残っているのも面白く、具材や汁といっしょにそれが口に入り、口内で潰れていく。粒を食べながら豚汁の旨さを実感するのだ。水でこれだけ風味が出るのだから、だしだとどうなるのだろうかと思っていると、それを見透かしたかのように浦上さんが「鰹だしの場合だと、料理屋で味わう豚汁といった感じになると思います。今日は水だけで作るという面白さを取っただけで、勿論だしで作った方がいいですよ。でも初めから種明かししましたが、言わなければ水だけで作ったとは思わなかったでしょ」と微笑みながら説明してくれた。

浦上さんの「しょうゆもろみ」評は、角がなく、優しい味なので使いやすいとのこと。どうしても関西人は角があると、辛いからと敬遠する傾向にある。だから「この味噌は、関西人には評価が高いでしょうね」とも言っていた。浦上さんは、この味噌を渡された時に焼物に使うなどをして表現しようかと思ったそうだ。ところがHPで「名料理、かく語りき」を読んでみると、他の人が同じような考え方をしていたので、それでは面白がらないだろうと思い、あえて汁物で表現してみたのだと話してくれた。こんなところが実に浦上さんらしい。かつては王道の日本料理ではなく、ハイブリッドな手法で「石和川」の名を目立たせ、誰もがハイブリッドを取り入れ始めると、一転して王道日本料理を追求する。伝手があったとはいえ、どこもが取引したくてしようがない明石浦漁協とパイプをつけて、他にはまねのできないような鮮度がよく、良質の魚の仕入れて、その素材に見合うような調理法を模索する。以前、我が友人の藤本喜寛先生(元辻学園TEC日調西洋料理教授)が、浦上さんをこう評していた。「名が売れると、板場に立たなくなる人が多い。そんな中で浦上さんは、いつも『石和川』のカウンターに立って調理をしている。そこが偉いのだ」と_。浦上さんは現在、女優の平愛梨さん(明石出身)とともに明石ふるさと大使を務めている。すでに街場の料理人ではなく、魚の町・明石を代表する人物になっている。なのに魚のセリ場に出かけ、自身で目利きし、それを自ら調理する。そこを藤本先生は評価しているのだと思われる。
-
<取材協力>
(閉店)粋餐 石和川(大阪・北新地)
住所/大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-9 第1三好ビル1~2階
TEL/06-6345-5588
営業時間/11:30~14:00 17:00~23:00
休み/日祝日
メニューor料金/
<昼>コース3000円、4000円、4500円、6000円
まぐろほほ肉カツ定食 1000円
焼魚定食 1000円
松花堂弁当 2000円
<夜>旬の会席コース 8000円、10000円、12000円、15000円、18000円
旬の天婦羅コース 8000円、10000円
日替わり一品料理
筆者紹介/曽我和弘
廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。